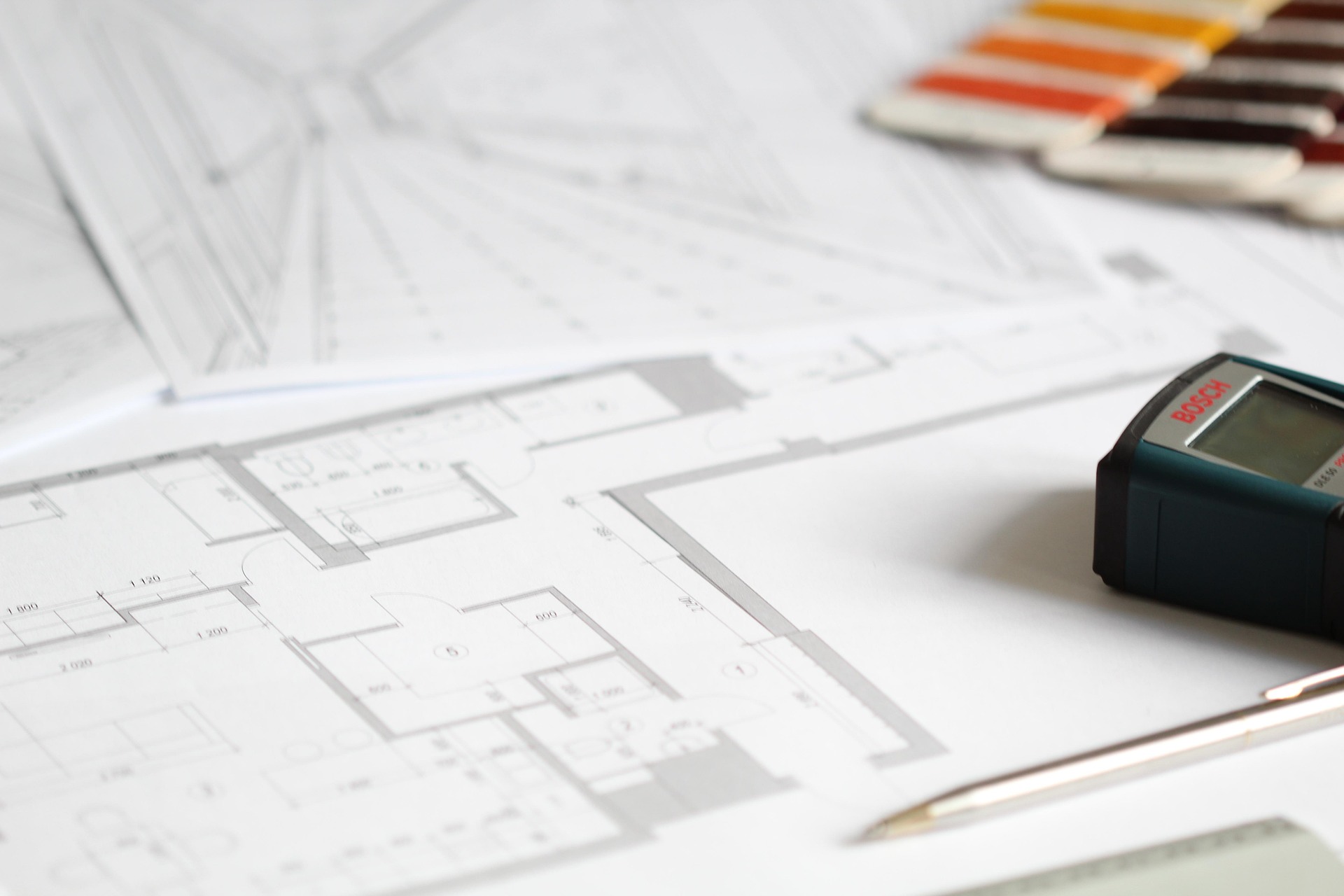「金属加工の超基礎解説」では金属加工の現場で登場する専門用語を、金属加工をほとんど知らない人でも理解できる言葉を使って紹介します。今回のテーマは寸法と測定です。
金属加工における寸法と測定は、実際に形をつくっていく鋳造や切削などと比べると地味かもしれません。しかし、ものづくりの世界には「寸法のない製品はない」「測定しないと完成しない」という言葉があるほど重要なものです。
寸法と測定が金属加工の品質を決める
ものづくりを次のように定義すると寸法と測定がどれほど重要であるかがわかります。
- ものづくりとは図面に書かれた寸法とおりにつくることである
- つくったものを測定して寸法とおりであることを証明できて初めて完成する
金属加工製品のなかには、図面にミクロン単位の寸法が書かれているものがあり、完成品が数ミクロンずれただけで不良品になることもあります。寸法と測定は、金属加工の品質を決めます。
寸法とは何か
金属加工における寸法とは、図面で指定された長さ、厚さ、直径、角度などの数値のことです。ただ寸法の重要性は単に数値の明示にとどまりません。寸法を適切に管理することで、製品の適合性や機能が確保されます。
例えば、金属加工部品Aと金属加工部品Bを組み合わせて製品をつくる場合、設計者はAとBの寸法を適切に設定します。この寸法が適切に保たれていれば、AとBは適合し、想定とおりの機能を果たします。しかし完成品の寸法が許容範囲を超えてしまうと、部品が適合せず、無理に組み立てても性能が低下する可能性があります。したがって寸法は、製品の品質や性能を左右する重要な要素となるのです。
寸法精度という概念
寸法の概念のなかで重要になるのは精度という概念です。精度とは正確さのことです。したがって寸法精度とは「図面で示された寸法に対し、完成した製品はどれだけ正確か」という考え方です。例えば、図面に長さ3mmと書いてあった場合、完成品の長さが2.9mmであれば寸法精度は高いといえますが、2mmであれば寸法精度は低いといえるでしょう。
JIS規格のなかの寸法精度
JIS規格では寸法精度を「JIS B 0405(1991)」という表で規定しています。「JIS B 0405(1991)」の表には、このように書かれてあります。
■JIS B 0405(1991)の表(一部抜粋、一部編集)
| 図面の寸法 | 0.5mm以上、3mm以下の寸法 | 3mm超、6mm以下の寸法 |
| f(精級) | 許容差±0.05mm | 許容差±0.05mm |
| m(中級) | 許容差±0.1mm | 許容差±0.1mm |
| c(粗級) | 許容差±0.3mm | 許容差±0.3mm |
| v(極粗級) | なし | 許容差±0.5mm |
f(精級)、m(中級)、c(粗級)、v(極粗級)は寸法精度の高さ(厳しさ)と低さ(緩さ)を示しています。fは高精度の製品に適用され、mは主に金属部品に適用され、cとvは主に樹脂部品に使われます。例えば、fの精度を必要とする金属部品をつくる場合、図面の寸法が0.6mmであれば、完成品は0.55mmから0.65mmの間でつくらなければなりません。
ここまでの説明で次の疑問が湧くと思います。
- 寸法精度は設計者が任意に決めることができるはずなのに、なぜJISで規定されているのか
例えば設計者が、ミクロン・レベルやナノ・レベルでの寸法精度が必要であると考えれば、fの精度でも足りません。それでもJISで「一応」寸法精度を決めておくのは寸法精度の標準化を図るためです。設計者が図面を描くたびに「今回の許容差は±0.04mmぐらいにしようかな」と決めるのは大変です。なぜ±0.04mmにしたのか、という根拠を示さなければならないからです。JISで決めておけば、設計者は「この製品は高精度が求められるからfにしよう」とすぐに決めることができます。
そしてJIS B 0405(1991)に書かれてある数値ですが、これは経験則や統計データに基づいて算出されたものです。例えば「fクラスの高精度の金属製品をつくりたい場合、図面の寸法が0.5mm以上、3mm以下であれば、許容差±0.05mmにしておけば大体問題ない」といえるわけです。
測定と測定ミスについて
測定とは、完成品が、図面で指示された寸法とおりになっているかどうかを測ることです。測定器具や測定機器を使って完成品を測り、許容差内(誤差が許容範囲内)に収まっていれば合格、許容差を超えていたら不合格となります。測定で重要になるのは、測定方法と測定ミス(をしないこと)です。測定方法については次の章で紹介するので、ここでは測定ミスについて解説します。
測定ミスが発生すると、不良品が顧客のところに届いたり、生産ラインに流れたりしてしまうでしょう。例えば自動車のエンジンの部品に不良品が混ざっていると、摩擦が想定以上に大きくなり燃費が悪化したり故障したりします。最悪、大規模リコールにつながります。
自動車のリコールの内容が深刻で重大事故を誘発する可能性がある場合などは、マスコミは主に自動車メーカーを報じますが、その自動車メーカーは金属加工会社などの部品メーカーを徹底的に調査します。その調査のなかで測定ミスが発覚すると賠償責任が問われることもありますし、何より金属加工会社としての信頼が大きく揺らぐことになるでしょう。図面に書かれた寸法が正しくても、寸法とおりにつくることができる技術を持っていても、測定ミスによって不良品が顧客の手に渡ってしまったらそれまでの努力が台無しになりかねないのです。
測定方法:器具と機器の種類と特徴
測定を行うには、主に手動式でアナログ式の測定器具や、主に電気式でデジタル式の測定機器を使います。測定器具・機器は、無数といっても大袈裟でないくらい多くの種類があるので、ここでは代表的なものだけを紹介します。
ノギスとマイクロメーター
手動・アナログ式の測定器具の代表格はノギスとマイクロメーターでしょう。
ノギスとは、本体(本尺)と、本尺に沿ってスライドする副尺からなる測定器具で、副尺の目盛を利用して寸法を読み取ります。ノギスは長さ、内径、外径などを測ることができます。ノギスの精度は0.05mm程度なので、測定により高い精度が求められるときはマイクロメーターを使います。こちらの精度は0.01mm単位となります。
三次元測定機
自動・デジタル式の測定機器の代表として、三次元測定機を紹介します。三次元測定機は、自動装置とコンピュータを使って、複雑な形状の製品を高精度に測定する機器です。三次元測定機には、細い棒状のプローブが付いていて、その先端には球形の接触子(スタイラス)が付いています。まずプローブを移動させて、測定したい部分(測定点)に接触子を軽く触れさせます。接触した位置の座標が、X、Y、Z軸の数値として記録されます。次に、別の測定点で同様に座標を取得し、2つの測定点の座標の差から寸法を求めます。
(雑談)測定の測定について
測定に関する雑談を。測定では、必ず「測定したので寸法とおりであるといえる」とはいえない事態が起こりえます。それは測定器具・機器が正確に測れない状態にあったり、測定の対象物が収縮・膨張することがあったりするからです。
正確な測定器具・機器をつくるには、正確に測定できる測定器具・機器で測定された部品を用意する必要があります。このように考えていくと、測定器具・機器Aをつくるための測定器具・機器Bが必要になり、測定器具・機器Bをつくるための測定器具・機器Cが必要になり…といった無限ループに陥ります。そして仮に「絶対に間違えない」測定器具・機器があっても、測定対象の製品が室温によって収縮・膨張してしまっては正確に測れません。
ある三次元測定機メーカーは、「この三次元測定機で正確に測るには、室温が一定に保たれる測定室を用意して、測定対象物を測定する5時間以上前に測定室に入れておくように」と指定しています。正確に測定することがとても難しいことがわかると思います。
公差とは
公差は、寸法と測定を理解するときにとても重要な要素になります。ここまでの説明ではあえて専門用語を使わず「誤差の許容範囲」と表現してきましたが、これが公差です。
あえて公差を設ける理由
公差は図面に記入されています。そこには上限値と下限値が記されていて、完成品の寸法がその範囲内に収まっていれば適切と判断されます。ではなぜ、あえて公差を設けるのでしょうか。つまり「必ずピッタリこの数値でつくれ」と指示するのではなく「この範囲内に収まるようにつくればよい」とするのはなぜでしょうか。
公差を設ける理由その1は、コスト削減と製造の効率化です。「必ずピッタリこの数値でつくる」ことになると、製造が難しくなりますし不良品もたくさん出ます。性能に支障が出ない範囲で公差を設けることで、コストと効率性をコントロールできます。
理由その2は、部品の組み合わせの柔軟性を確保することです。部品Aと部品Bを組み合わせて製品をつくるとき、AとBを完全に寸法とおりにつくってしまうと、材質が収縮したり膨張したりすることで組み立てられなくなることがあります。組み立てやすくするように、あえて寸法に余裕を持たせるわけです。
寸法公差とは
公差のうち寸法公差とは、設計上許容される寸法の範囲のことです。例えば、直径10.00mm±0.05mmと指定された場合、9.95mmから10.05mmの範囲内であれば合格となります。
幾何公差とは
公差のうち幾何公差は、形状や位置関係に関する許容範囲を定めたものです。例えば、平行度は2つの面や2つの線がどれくらい平行かを示す数値ですが、平行度の公差は幾何公差になります。
位置度は、完成品の特定の点が、図面で指定された点からどれだけずれているかを示します。例えば、ボルト穴の位置がずれていると、部品を組み合わせたときに正しく装着できず、製品の組立て精度に影響を及ぼします。位置度の公差を設定することで、部品が正確に組み合い、製品全体の性能や信頼性を確保できます。
技術やスキルと並ぶ重要要素
まったく同じ工業製品でも、壊れにくい個体とすぐに壊れる個体があるのは、この製品を構成する部品が正確か不正確かの違いです。「日本製は壊れない」という神話が存在するのは、日本の製造業会社が使っている部品の正確さが、他国の製造業会社が使っている部品の正確さより高いからです。
部品を正確につくるには、製造技術や製造者のスキルだけでなく、寸法と測定、そして公差の考え方が欠かせません。この3つの要素をないがしろにすると金属加工製品の品質はどこまでも落ちていきます。